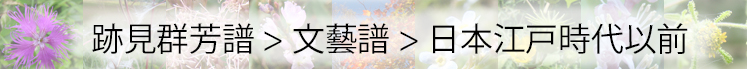
『万葉集』中、フジをよむ歌
長歌
| ・・・ をふの浦に 霞たなびき 垂姫に 藤浪咲きて ・・・ 反歌 藤なみの 花の盛りに かく(如此)しこそ 浦こぎ廻(み)つつ 年にしのはめ (19/4187;4188, 大伴家持) 此間(ここ)にして そがひ(背向)に見ゆる わがせこ(背子)が 垣つの谿(たに)に あ(明)けされば 榛のさ枝に 暮(ゆふ)されば 藤の繁みに 遥遥(はろばろ)に 鳴く霍公鳥(ほととぎす) ・・・ (19/4207,大伴家持) ・・・遥遥(はろばろ)に 喧(な)く霍公鳥 立ちく(潜)くと 羽触(はぶり)にちらす 藤浪の 花なつかしみ 引き攀じて 袖にこき(扱入)れつ 染まば染むとも 反歌 霍公鳥 鳴く羽触にも 落(ち)りにけり 盛り過ぐらし 藤なみの花 (19/4192;4193,大伴家持「霍公鳥並びに藤の花を詠む一首」) ふじなみは さきてちりにき うのはなは いまそさかりと あしひきの のにもやまにも ほととぎす なきしとよめば ・・・ (17/3993,大伴池主) |
短歌
| 恋ひしけば 形見にせむと 吾が屋戸に 殖ゑし藤波 今開(さ)きにけり (8/1471,山部赤人) 藤浪の 花は盛りに 成りにけり 平城京(ならのみやこ)を 御念(おも)ほすや君 (3/330,大伴四綱) いも(妹)がいへ(家)に いくりのもり(森)の 藤の花 いまこ(来)む春も つね(常)かく(如此)し見む (17/3952,僧玄勝か) 霍公鳥(ほととぎす) 来鳴き響(とよも)す 岡辺なる 藤波見には 君は来じとや (10/1991,読人知らず) (天平勝宝2年4月)十二日、布勢の水海に遊覧し、多祜(たこ)の湾に 船泊して、藤の花を望み見て各々懐を述べて作る歌四首 藤なみの 影なす海の 底清み しづく石をも 珠とそ吾が見る (19/4199,大伴家持) 多祜の浦の 底さへにほふ 藤なみを かざして去(ゆ)かむ 見ぬ人の為 (19/4200,内蔵忌寸縄麿) いささかに 念ひて来しを 多祜の浦に 開ける藤見て 一夜経ぬべし (19/4201,久米広縄) 藤なみを 借廬(かりほ)に造り 湾廻(うらみ)する 人とは知らずに 海部(あま)とか見らむ (19/4202,久米継麿) はる(春)べさく ふじ(藤)のうら葉の うらやすに さぬ(寝)る夜そなき 児ろしも(思)えば (14/3504,読人知らず) 藤浪の 咲ける春野に 蔓(は)ふ葛の 下よし恋ひば 久しくも有らむ (10/1901,読人知らず) 藤浪の 散らまく惜しみ 霍公鳥 今城の岡を 鳴きて越ゆなり (10/1944,読人知らず) ふじなみの しげ(繁)りはす(過)ぎぬ あしひきの やま(山)ほととぎす などかき(来)な(鳴)かぬ (19/4210,久米広縄) (ほととぎす) あすのひ(日)の ふせ(布勢)のうらみ(浦廻)の ふじなみに けだしき(来)な(鳴)かず ち(散)らしてむかも (18/4043,大伴家持) 春日野の 藤は散りにて 何をかも 御狩の人の 折りて挿頭(かざ)さむ (10/1974,読人知らず) ・・・俗の語に云はく、藤を以て錦に続ぐと ・・・ (17/3966題詞;3969題詞, 大伴家持) |
枕詞「ふじなみ(藤浪・藤波)の」(思ひまつはり、ただ一目、たつなどにかかる)
| しき嶋の やまとのくにに 人多(さは)に 満ちて有れども 藤浪の 思ひ纏はり ・・・ (13/3248,読人知らず) かくしてそ 人は死ぬと云ふ 藤浪の 直(ただ)一目のみ 見し人故に (12/3075,読人知らず) |
枕詞「ふじごろも(藤衣)」(折る、なる、まどおなどにかかる)
| 大王の 塩焼く海人の 藤衣 なれはすれども いやめづらしも (12/2971,読人知らず) 須磨の海人(あま)の 塩焼衣(しほやきぎぬ)の 藤服(ふじごろも) 間遠にし有れば 未だ着なれず (3/413,大網人主) |
| 跡見群芳譜 Top | ↑Page Top |